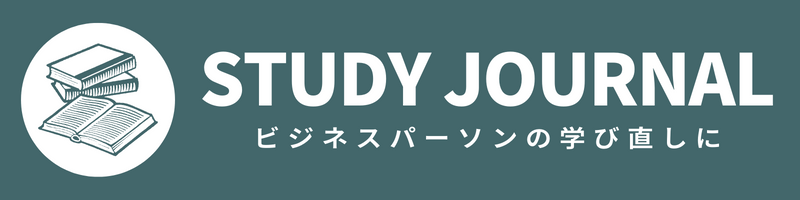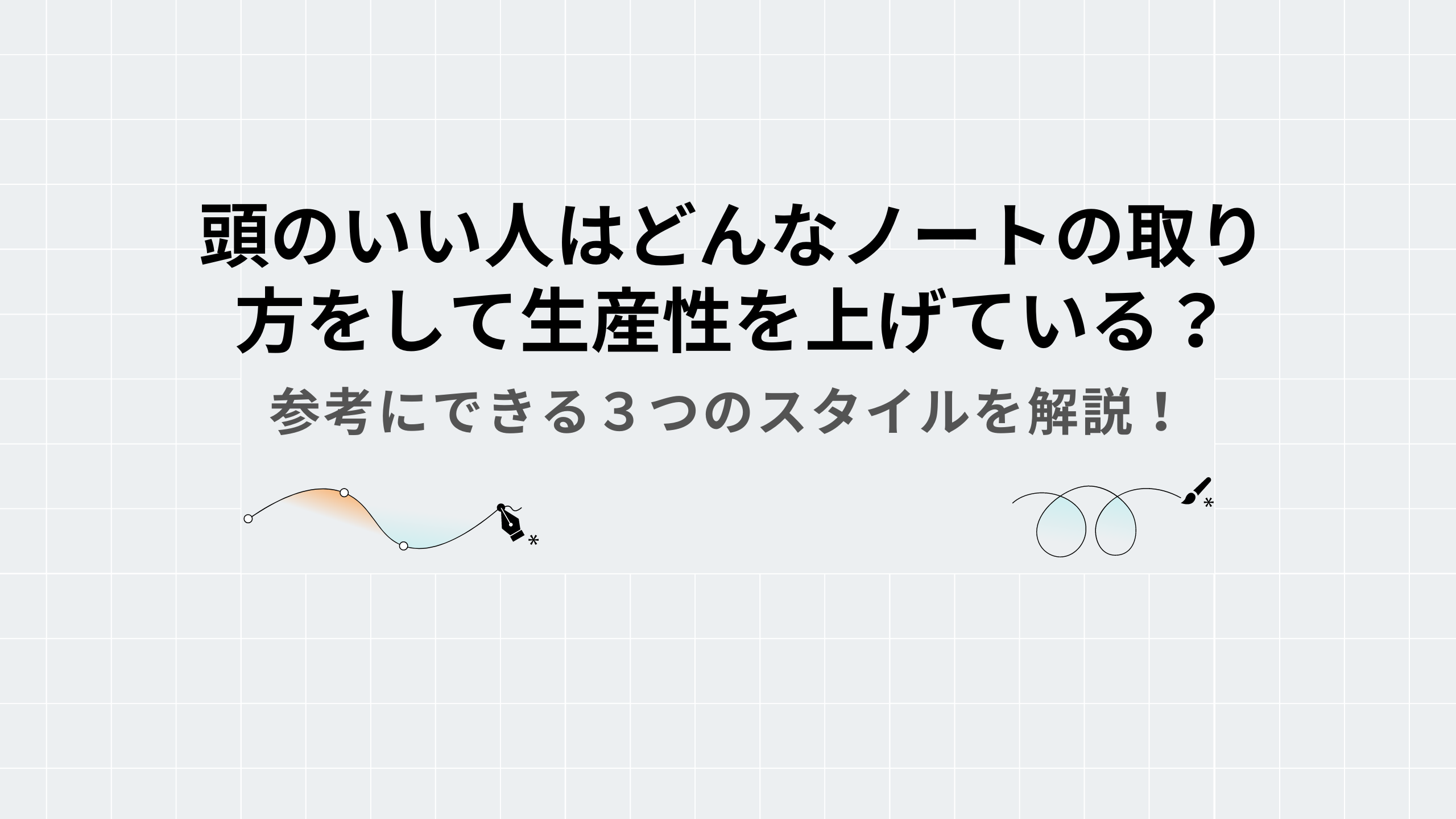ビジネスパーソンの皆さんは普段、日々の仕事のなかでノートを取っているでしょうか。
「ノートを取る」というと子供や学生の学習方法のように感じるかもしれませんが、仕事の生産性を上げることにも役立つ方法の一つです。
ビジネスパーソンが新たなスキルを獲得しようとするとき理解することと記憶することが壁になることがありますが、ノートの取り方1つでそれらの壁を乗り越えられるかもしれません。
ただ、単にノートを取るだけでは生産性向上につながらない場合があります。ではどんなノートの取り方が良いのかというと、頭がいい人やデキる人たちのノートが参考になります。
頭が良い人たちのノートの取り方には特徴やルールがありますので、その特徴やルールを理解したうえで習慣化すれば、誰でも効果をあげることができるでしょう。それでは早速、ビジネスで役に立つ、3種類のノートの取り方を解説していきます。
頭がいい人が実践するノートの取り方:3つのスタイルを紹介
頭がいい人が実践しているノートの取り方にはいくつかスタイルがありますが、この記事では次の3つのスタイルを紹介します。
- 基本を重視したノートの取り方
- 詳細を書き込むノートの取り方
- 実用性を重視したノートの取り方
ノートの取り方のスタイルは、何を重視するかで変わってきます。それでは、1つずつ解説していきます。
①基本を重視したノートの取り方:記号、補足、まとめの3原則を守る
頭のいい人、デキる人のノートをのぞくと意外と普通さに驚くかもしれませんが、そこには何の変哲もない記述が広がっています。
ビジネスでは経験が多い人ほど基礎を大切にしますが、ノートの取り方をとっても同じことが言えます。
基本重視スタイルの3原則は以下のとおりです。
- 記号
- 補足
- まとめ
ノートの取り方で自身のスタイルが定まっていない人は、まずはこの基本重視スタイルを試してみてはいかがでしょうか。
記号とは何か、なぜ記号が重要なのか
ここでいう記号とは、ノートの記述につける記号のことです。
記号の種類や形状はなんでもよく、自分で理解できればそれで構いません。一先ずは分かりやすく、「◎○△×」を使ってみてはいかがでしょうか。
そして、使う記号を決めた後は、記号に意味を持たせます。例えば◎は最重要事項、×は些末なこと、といったように決めます。
ノートに何か記述したら、その文頭に記号をつけていきます。記号をつけることで、あとでノートを見返すときに「今回は◎だけ確認しよう」とか「×をつけたが、意外にこういうところにヒントが隠れているかもしれない」と考えながら振り返ることができます。
また、記号を使うことで、ノートの記述に意味や価値を持たせることができるだけでなく、より深く理解できるようになるでしょう。
補足とは何か、なぜ補足が必要なのか
ノートにはみたことや聞いたことを書いていくわけですが、みたことや聞いたことを理解せずに、ただ書いただけでは学習になりません。そこで、自身が理解しきれていないことを書き込んだあとには、必ず理解が深まるように調べた上でノートに書いていきましょう。これが補足になります。
例えば自分が出席した会議で社長がスピーチをして、本の一節を引用したとします。このときノートに社長の言葉と一緒に本のタイトルを書いておきましょう。そして会議のあとでその本について調べて大体の内容を書き加えます。こうすることで社長の真意をより深く理解することができますし、記憶への定着も進みます。
まとめとは何か、なぜまとめを作成したほうがよいのか
ノートを取り続けると、情報量が膨大になります。情報量が一定量を超えると理解も記憶も追いつかなくなり、それではノートを取る効果が薄れてしまいます。
そこで、まとめる作業が重要になってきます。
ノートのなかの情報が一定量に達したら、そこまでの内容をまとめて書いていきます。例えば「3~5ページまでのまとめ」というタイトルをつけて、ノートの3~5ページに書いた内容を、自分の言葉でまとめていきます。ノートを読み返す時間が短いときは、まとめだけを読めば記憶を呼び出すことができるでしょう。
②詳細を書き込むノートの取り方~6つのルールを厳格に守る
詳細を書き込むノートの取り方もスタイルとしてあります。このスタイルは、自分で書きこんだノートを参考書のように使いたい人が用いる方法です。
ノートを参考書のように使う人は1冊の本をつくるかのように構成まで考えて書いていきます。このスタイルは、ノートを備忘録の代わりに取るスタイルとはかなり異なります。
このスタイルで作ったノートは自分の言葉で書かれてあるので、自身にとっては、市販の参考書より内容を理解しやすくなるでしょう。
ただし、参考書レベルにまで引き上げるにはノートに詳細に書き込んでいく必要があり、そうなるとノートの情報が増えてしまうので整理が欠かせません。
その際には6つのルールにしたがって書いていくとよいでしょう。
ルール1:文字の大きさをわける
参考書に限らず新聞でも雑誌でもプロの編集者がつくる読み物は、文字の大きさをわけています。文字の大きさを変えることで、情報の価値の違いを読者に伝えることができるからです。
価値が高い情報は大きな文字で記述して、少しだけ強調したいときは中くらいの文字で書き、説明文は小さな文字で記載します。
ノートを取るときも、このルールで文字の大きさを使い分けていきましょう。
ルール2:構成をつくる
参考書には必ず構成があります。構成とは「類似情報をくくること」と「くくった情報の塊を並び替える」ことです。
複数の情報のなかには類似したものがあり、それらをくくって情報の塊をつくることで、その情報に関する知識を集中して獲得することができます。
そして「くくった情報の塊」は、ほかの「くくった情報の塊」と関連することがあるので、両者を理解がしやすいように配置します。
構成を行うには、部、章、節を使うとよいでしょう。大きなくくりを「部」、中くらいのくくりを「章」、小さいくくりを「節」にします。
例えば、「第1部 マーケティング」「第1章 顧客の設定」「第1節 ビジネスパーソンの分析」といったように構成していきます。
ルール3:補足的な情報を別途記載する
補足的な情報は不要な情報ではありません。不要な情報はわざわざノートに記載する必要はありませんが、些末であると感じられてもいつか使うかもしれない情報はノートに書いておく必要があります。
しかし、補足情報を重要な情報と同じレベルで記述してしまうと、あとでノートを見返したときに区別がつきません。
そこで補足情報を記載するスペースを、例えばノートの右下に確保しておき、重要な情報と隔離して記載していきます。
ルール4:重要なところや難解なところを強調する
ノートを取る最終目的は、理解して記憶することです。極論をいえば、ノートに書かれた内容をすべて理解して記憶できたらそのノートは捨ててしまっても構わないということになります。そのため究極のノートとは、理解できない内容と記憶しづらい内容さえ書いてあればよいことになります。
そのため、ノートを取る際には強調することを忘れないようにしてください。重要なところや難解なところ、覚えづらいところは、ノートを見返したときに真っ先に目のなかに入ってくるように書き残しておきましょう。
ルール5:色を使う
ノート取りにおいて文字の色は重要です。黒と赤と青の3色があるだけでもノートの見栄えが格段によくなります。そして見栄えがよいノートは、見返そうという気持ちになります。
色の使いわけは、先ほど紹介した補足情報の整理や強調に使うことができます。
ルール6:自分の言葉で解釈する
ノートにみたことや聞いたことを記述したら、それを自分の言葉で翻訳し、それもあわせて書いておきましょう。
例えばノートに「AがBしたらCになった」と書いたとします。このときAとBとCについてよく理解していなかったら、その下に「Aとはつまりaであり、Bとはつまりbであり、Cとはつまりcである」と自分なりの解釈を書き足しておきます。
③実用性を重視したノートの取り方~小ノート×2、普通ノート×1の計3冊で対応
ノートに書いた知識や情報をそのまま仕事に使うことがあると思います。このときのノートは「やることメモ」や「マニュアル」になります。
ノートに書いたことを理解したり記憶したりする前に、まずはそのノートを使って仕事を進めたい、と思っている人は、このような実用性を重視したスタイルがおすすめです。
このスタイルではノートが3冊必要になります。
3冊の内訳
実用重視スタイルの3冊のノートの内訳は、手の平サイズの小ノート2冊と、普通のA4判のノート1冊です。
■3冊の内訳
- 小ノート(その1)
- 普通のノート(A4判)
- 小ノート(その2)
A4判のことを「普通」と呼んでいますが、特にこだわりがなければノートはA4判がおすすめです。コピー用紙もA4が標準なので慣れた大きさですし、ビジネスバッグもA4判を想定しているものが多いので持ち運びにも困らないはずです。またA4判は大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズなので書き込みやすいでしょう。
ステップ1:小ノート(その1)に乱雑に書いていく
小ノート(その1)は、職場でとにかくメモを書きまくるためのものです。乱雑になってもかまいません。自身で読める字であればよく、誤字脱字も気にしないで書いていきます。
その代わり職場で見聞きしたものはすべて書き写すようにしてください。ノートを取るときは、必要な情報か不要な情報か、価値ある情報かそうでない情報か、といったことを考える必要はありません。
ステップ2:普通のノート(A4判)に清書する
小ノート(その1)に殴り書きした内容を、普通のノート(A4判)に清書しながら書き写していきます。文字の大きさや色を変えたり、構成を考えたりして、あとで読み返しやすいようにしてください。
ステップ3:小ノート(その2)に必要最小限の情報を書き写す
2冊目の小ノート(その2)は、普通のノート(A4判)に書いた情報のなかから、1)職場で使う知識、2)どうしても覚えられない内容、をピックアップして書き写していきます。これが「マイ作業マニュアル」になります。
職場で作業するときは、この小ノート(その2)をみながら仕事を進めていきます。A4判ノートでは大き過ぎる場合もありますので、手の平サイズの小ノートならポケットに忍ばせておけます。
そして「小ノート(その1)→普通ノート(A4判)→小ノート(その2)」と、同じことを3回書いているので記憶への定着はかなり確実になるはずです。
学習効果を効率的に獲得するなら
記事の内容を箇条書きでまとめます。
- ノートを取ることはビジネスパーソンの学習にも有効
- 基本重視スタイルは記号、補足、まとめを駆使する
- ノートを参考書にするなら詳細を書き込む
- 実用性を重視するなら3冊のノートを用意する
大人になるとなぜかノートを取る習慣が消えてしまいます。しかし学校の先生たちが子供たちにノートを取るように指導するのは学習効率が上がるからです。
ビジネスパーソンこそ学習効果を効率的に獲得したいはずですので、ノートを取らない理由はないでしょう。
ぜひこの記事でご紹介したノートの取り方を参考にしていただき、仕事の生産性を高めてみてはいかがでしょうか。